主要7チャネルの強み・弱み分析
| チャネル | 強み | 弱み |
|---|---|---|
| 百貨店 | 高価格帯ブランドの信頼感/丁寧な接客 | 来店頻度の減少/若年層の離脱 |
| 化粧品専門店 | 地域密着/接客力の高さ | 店舗老朽化/若年層との接点不足 |
| 量販店 | 価格競争力/生活動線上での立地 | ブランディングが弱い/棚取り競争激化 |
| バラエティストア | トレンド感/SNS拡散との親和性 | 商品回転が早く定番化しにくい |
| ドラッグストア | 圧倒的な来店数/医薬品との相乗効果 | 商品情報提供が不足/価格重視傾向 |
| 通販(EC・紙) | 購入の手軽さ/D2Cに最適 | 実物確認できず離脱リスクあり |
| 訪問販売 | 密な関係性/高単価商品に強い | 新規顧客開拓の難しさ/時代とのギャップ |
社会・購買行動の変化から見た今後の市場構造予測
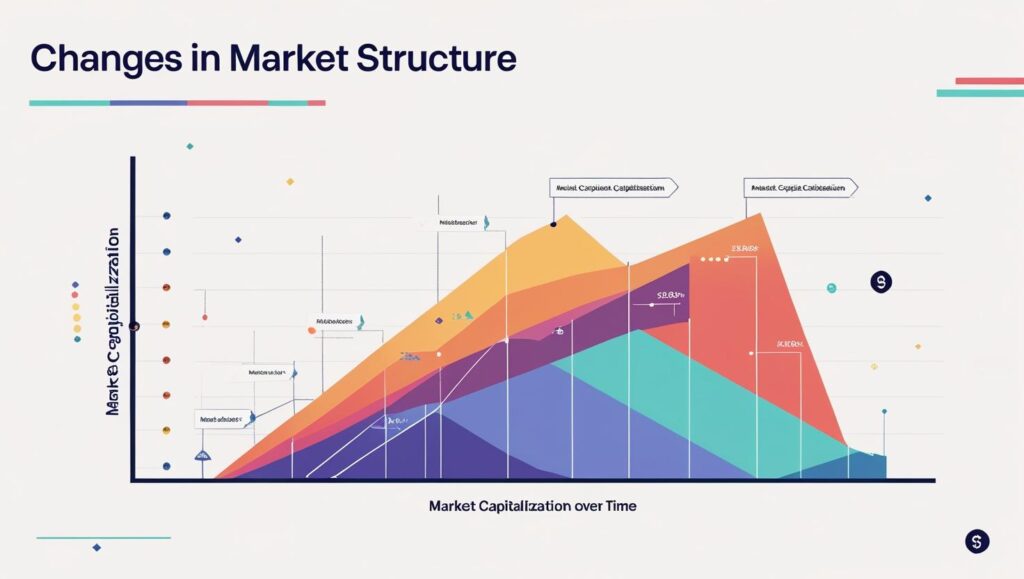
- 「体験しなくても買える」時代の到来
動画・レビュー・AIレコメンドの発達により、テスターがなくても購入できる環境が整いつつある。特にZ世代・α世代は情報で化粧品を買う傾向が強く、SNS×ECの連動は今後さらに加速。 - 「場所」に依存しない消費行動
リアル店舗の“わざわざ行く価値”が問われる中、百貨店や専門店は体験型・イベント型・パーソナライズ型への進化が求められる。訪販ブランドもモール出店やEC強化で再成長を遂げており、チャネルの垣根があいまいに。 - 卸中心のバラエティ/ドラッグストアは“棚”の価値が下がる
店舗で商品を知り、ネットで買う「ショールーミング化」が進行。仕入れバイヤーとブランドの関係性に加えて、SNS人気や販売戦略が採用判断に影響するように。
今後必要な販売戦略の結論

✔ “チャネル単体”ではなく、“体験×流通×情報発信”の三位一体で考えるべき時代
✔ ブランド側は、複数チャネルのハイブリッド戦略と、チャネル別にカスタマイズされた商品・情報発信が必須
✔ 「どこで売るか」より「どう売るか」「どう届けるか」が主戦場に
たとえば、百貨店でプレミアムラインを展開しつつ、ECではサンプル付きスターターセットを販売するなど、チャネルごとの役割分担と訴求設計が重要となります。
まとめ
日本の化粧品流通は多様で強固なインフラを持つ一方、購買行動の多様化と情報接触の進化により、チャネル戦略の再構築が急務です。これからのブランドには、「どこで売るか」よりも「誰にどう届けるか」という視点が求められます。単なる流通選定ではなく、ブランド体験の届け方そのものを設計することが、次の時代の勝ち筋です。

