中国発のキャラクター「LABUBU(ラブブ)」は、アーティストの世界観+POP MARTの商流設計(ブラインドボックス・限定・リアル販促)+SNS(セレブ投稿含む)で一気に拡散。バズを起点に「所有欲×見せる消費」を設計すれば、ブランド化と高付加価値化が可能になる。ただし供給コントロールや二次市場の暴走には注意が必要。
ラブブ(LABUBU)とは?

ラブブは香港出身のイラストレーター Kasing Lung(龍家昇)が生んだキャラクターを元に、POP MART(ポップマート)が商品化したアートトイ/ぬいぐるみシリーズです。愛らしいながら少し不敵な顔つきが特徴で、コレクターズトイとして展開されてきました。
ヒットの起点 — 何が火をつけたか
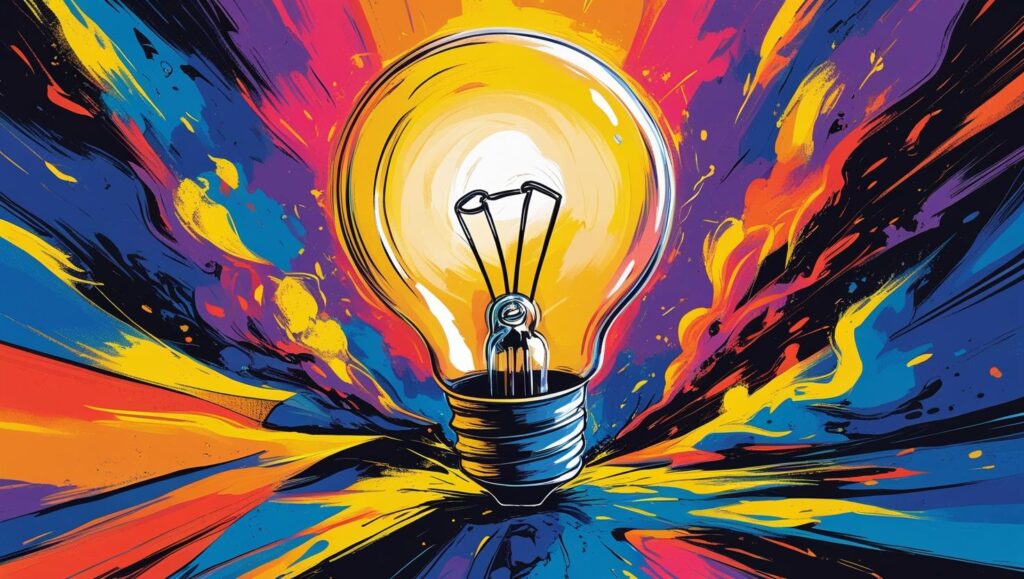
- POP MARTによる「ブラインドボックス(盲箱)」やバッグチャーム化、実店舗発売の戦略で“買う行為そのもの”をイベント化。バージョン3.0の発売では世界各地で行列が生まれ、公式アプリのダウンロードランキングを押し上げるほどの反響が出ました。
- TikTok・Instagram上でのUGC(開封動画・着せ替え・コーデ投稿)が雪だるま式に広がり、有名人やセレブの投稿がさらに注目を集める“信頼ある拡散”を生みました。結果としてトイ分野の“見せる消費”が加速しています。
経営者が学ぶべき「ヒットの仕組み」5つ

1)「強い世界観」と「単純な識別子」
キャラクター自体が一目で認識でき、物語(アーティスト由来のストーリー)を持つことで、長期的なファン化が可能に。商品開発はまず“世界観設計”から。
2)所有欲を刺激する商品設計(ブラインド+限定)
中身が分からない盲箱は“もう一回買いたくなる”仕掛けです。限定モデルやシークレットを混ぜることで二次流通や話題化が起きます。POP MARTのようにアイテム差別化を明確に設計することが肝。
3)オムニチャネルでの“見せる”販売体験
実店舗(列)→SNS(動画)→公式アプリ(ランキング)という流れで、買う行為自体がコンテンツになる設計。オンラインとオフラインの接点を意図的に作ること。
4)インフルエンサー/セレブの戦略的活用
有名人の使用・投稿はトレンド加速のスイッチになります。だが単発で終わらせず、ブランドとユーザーをつなぐ継続施策に昇華させることが重要。
5)需給管理とマーケットメイキング
供給を絞れば希少性はあがるが、転売やバブル化のリスクも伴う。POP MARTの事例からも分かるように、過度な投機には市場が反応するため、価格管理・流通監視は必須。
リスクと注意点

- 二次市場の暴走:転売価格の上昇とバブル崩壊はブランドの信頼を損なう。規制・保証・正規流通の強化が必要。
- 一過性のバズ依存:バズだけでブランドは続かない。継続的な商品更新とコミュニティ育成が不可欠。
- 品質とコストのバランス:低品質で短期的に売れても長期の顧客は失いやすい。
1分でできる実践チェックリスト(経営者向け)
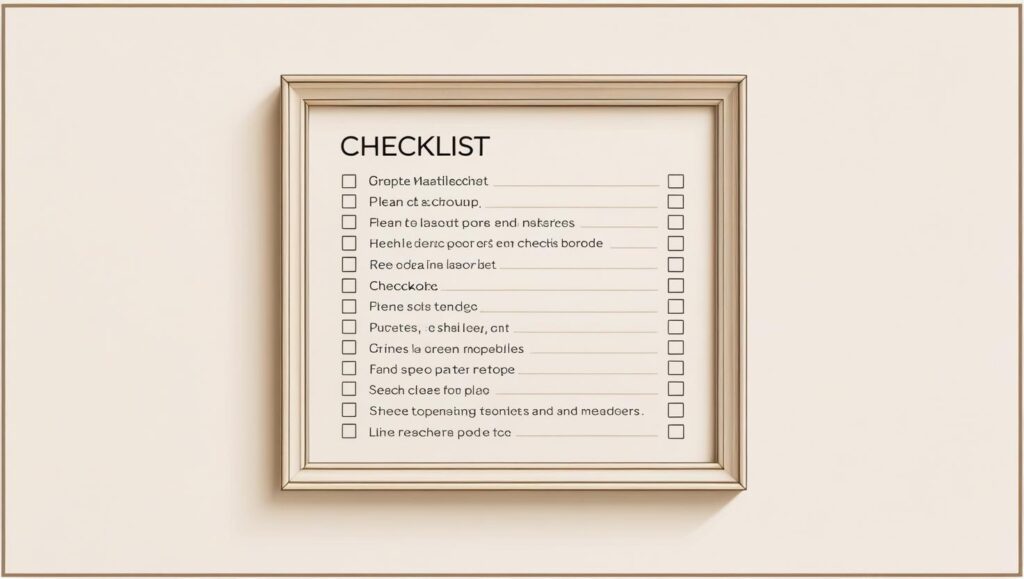
- 商品の「世界観」を3行で定義する(ターゲット/ストーリー/象徴)。
- 盲箱や限定を導入する際は「限定率(%)」と「シークレット率」を決める。
- 発売前に小規模なリアルイベント+UGCキャンペーンを計画。
- セレブ/インフルエンサー起用は“認知”だけで終わらせず、限定特典で“所有”に繋げる。
- 二次流通を監視し、必要なら公式BUY BACKや正規リセールを検討する。
まとめ
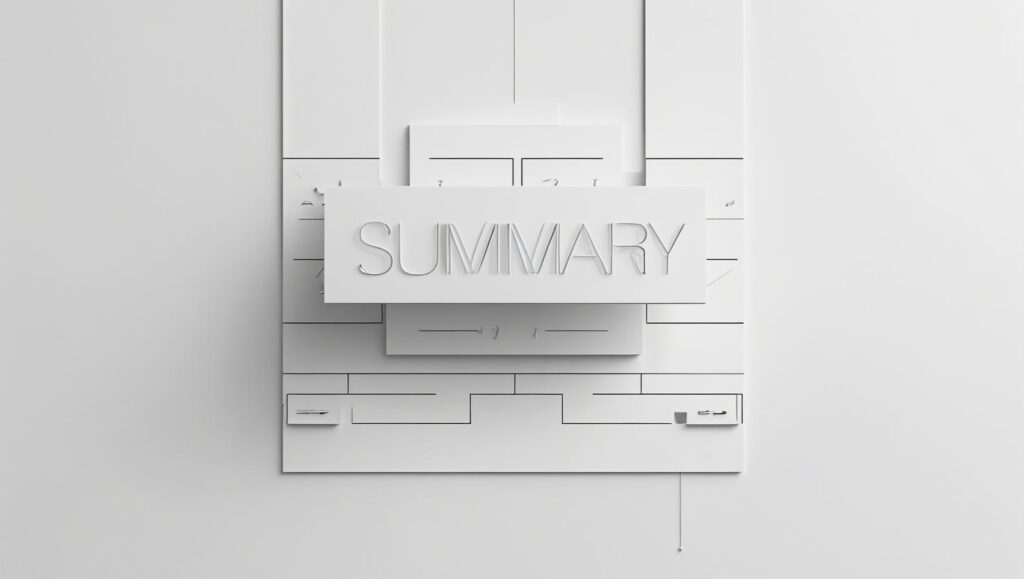
ラブブの急成長は「良いキャラクター」×「仕掛けられた購買体験」×「SNS拡散」の三拍子が揃った結果です。流行を追う経営者は「バズを起点にした商品設計」「供給管理」「継続的な世界観の更新」をセットで考えること。短期的なバズに飛びつくだけでなく、二次市場やブランド価値まで見越した設計が、ヒットを“持続可能”にします。

